地震で建物が倒壊した場合の責任は?
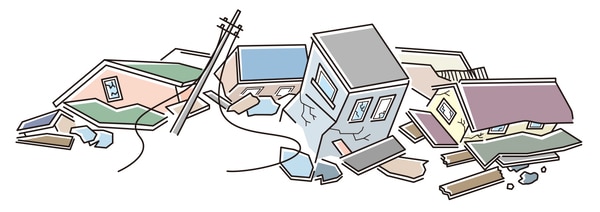
目次[非表示]
自然災害発生時の基本的な視点
地震被害による建物倒壊など、甚大な被害が発生するのが、自然災害発生時の特徴です。
東日本大震災発生後のトラブルでは、住宅会社には故意も過失もないとして裁判で争うことを選択した案件もありましたが、何年も裁判をした結果、裁判所から足して2で割る和解案の提示を受けることもあり、「こんな結論になるくらいなら、裁判などしなければよかった」と後悔をしたケースもありました。
このとき学んだことは、自然災害発生時の基本的な対応方針としては、施主と住宅会社が手を取りあって困難に立ち向かうという姿勢が大事であるというスタンスの取り方でした。
自然災害を前にして、皆が被害者であり、住宅会社も被害者のうちの一人です。敵対視し合わない対応が非常に重要です。
建物崩壊の責任(施工者の施工に問題があった場合)
case 01 施工に問題があり、建物が倒壊してしまった。その責任は...
住宅会社が施工し、完成・引渡しをした建物が、地震で倒壊。筋交いが予定されていた場所に入っていなかったり、構造上、問題が生じる施工をしてしまっていたことが判明。

争点
地震被害発生の際は、この建物の周辺一帯が、極めて強い地震に見舞われ周辺一帯の建物が倒壊しているというケースもある。建物に施工の瑕疵がなかったとしても、倒壊していた可能性もあり、この場合でも法的責任を負わなければならないのかが問題となる。
case 02 地震により賃貸マンションの一部が倒壊し、貸借人が死亡した。その責任は...
阪神・淡路大震災(現行の設計震度をも上回る揺れの地震)により、賃貸マンションの一階部分が倒壊し、賃借人が死亡した。

神戸地裁 平成11 年9 月20日 判決 損害賠償は5割に
倒壊した賃貸マンション自体が、建築当時を基準に考えても、通常有すべき安全性を有していなかった建物であることが前提だが、そこに自然力である地震が加わった場合の責任の有無に関する因果関係の判定及び損害発生に対する寄与度の考え方において、次のように判示した。
「(前略)本件のように建物の設置の瑕疵と想定外の自然力とが競合して損害発生の原因となっている場合には、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨からすれば、損害賠償額の算定に当たって、自然力の損害発生への寄与度を割合的に斟酌するのが相当である。(略)地震の規模・被害状況等からすると5 割と認めるのが相当である。」
秋野弁護士のポイント解説
case02 は土地工作物である建物が倒壊し、人が死傷した場合の損害賠償事案で、「倒壊状況」が重要となりました。「建物自体の倒壊に対する責任」の判断においては、周辺一帯の建物全てが倒壊している状況に照らせば「いずれにせよ倒壊していた」として、損害に対する因果関係が否定されるという考え方もあり得ますが、他方で、裁判所が構造欠陥の存在を見過ごすことはないと思われるため、裁判となれば50%前後の損害負担を求められる可能性があります。
地震被害発生時には、今まで対応したことのないトラブルが生じるケースがあり、しっかりと住宅会社の立場になってサポートしてくれる弁護士に伴走してもらいながら、困難を克服していく対応をしていただきたいと思います。

秋野卓生(あきの たくお)
弁護士法人匠総合法律事務所代表社員弁護士として、住宅・建築・土木・設計・不動産に関する紛争処理に多く関与している。
2017年度より、慶應義塾大学法科大学院教員に就任(担当科目:法曹倫理)。管理建築士講習テキストの建築士法・その他関係法令に関する科目等の執筆をするなど、多くの執筆・著書がある。
【役職等】
平成16年〜平成18年 東京簡易裁判所非常勤裁判官
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会理事・法律顧問弁護士
一般社団法人住宅生産団体連合会消費者制度部会コンサルタント
令和6年度 日本弁護士連合会常務理事、第二東京弁護士会副会長
COLUMN
建物に関する法的責任・不法行為責任とは…
築10 年以上の建物については、瑕疵担保責任(新民法における契約不適合責任)は問題とならず、不法行為責任の成否が問題となります。
施工者が建築した建物について不法行為責任を負う要件として、「①設計・施工者等が基本的な安全性に配慮すべき注意義務を怠ったために、②建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵が存在し、③それにより、④居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、⑤不法行為の成立を主張する者が瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情のない限り、不法行為が成立する」と判示。(最高裁 平成19 年7月6日判決)
「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」が認められる場合、施工者は不法行為責任を負うことになります。



