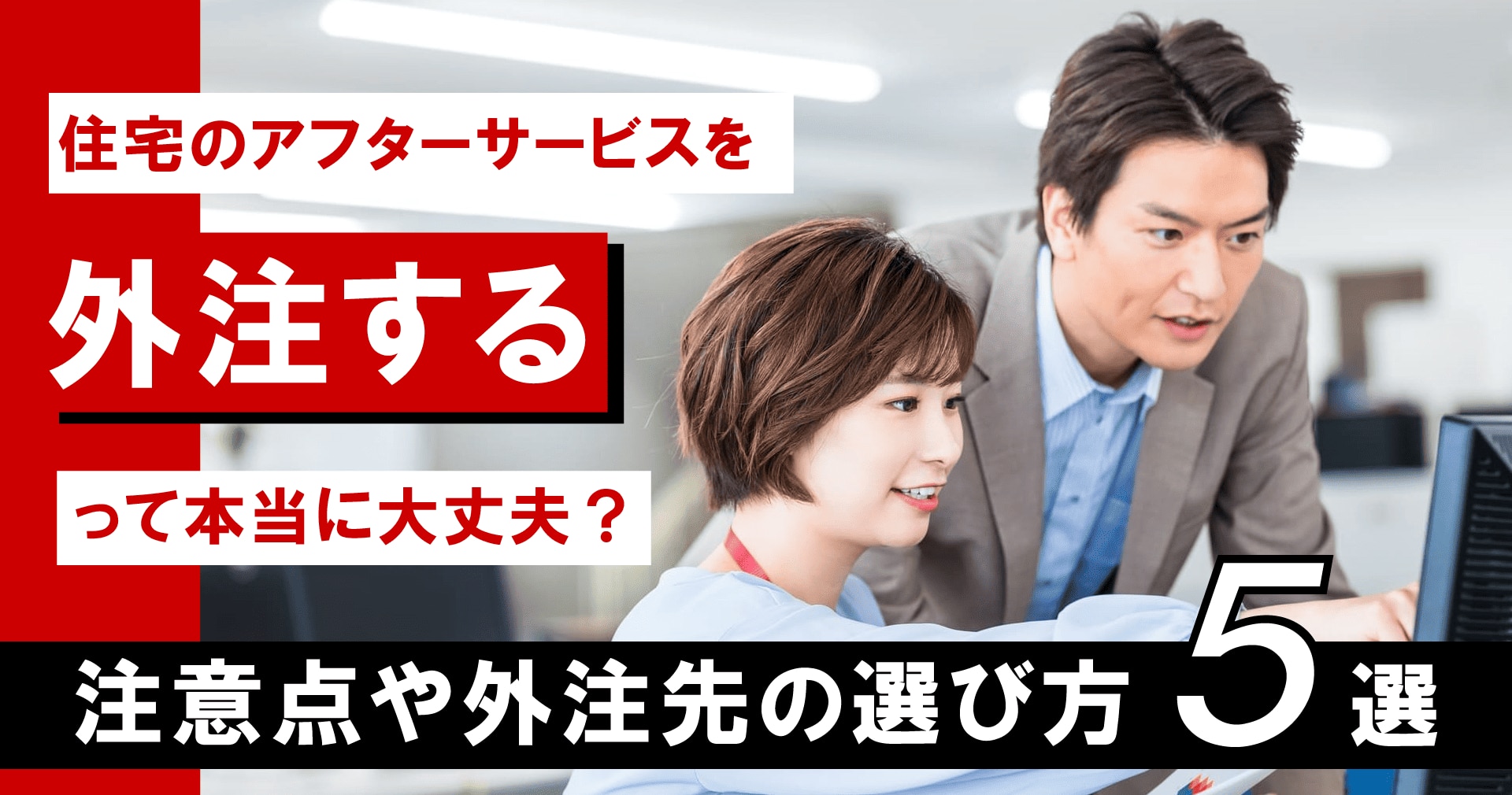
住宅のアフターサービスを「外注」って本当に大丈夫? 注意点や外注先の選び方5選
これまで住宅会社のアフターサービスは、社内スタッフによる対応が主流でした。しかし近年、施主のアフターサポートに対する期待が高まる一方で、人手不足や人材育成の負担から、外注を検討する住宅会社も増えています。一方で、「外注先に任せて本当に大丈夫か?」と不安を感じる声も少なくありません。
そこで本記事では、住宅会社の「アフターサービス外注に対する不安」に触れながら、施主との関係構築を成功させるための「外注」の活用ポイントについて解説します。
この記事で分かること=========
・住宅会社が抱えるアフターサービスに関する課題
・アフターサービス外注を検討する際の3つの注意点
・アフターサービス外注先を選ぶ5つのチェックポイント
==================
目次[非表示]
- 1.住宅会社が抱えるアフターサービスの課題とは?
- 2.アフターサービスの外注に対してなぜ不安を感じてしまうのか?
- 3.アフターサービスの外注検討の際に注意すべき点3選
- 3.1.注意点①|施主との対応窓口を一元化しておくこと => 施主対応の標準化
- 3.2.注意点②|過去の対応内容を管理しておくこと => 対応品質の見える化
- 3.3.注意点③|内製と外注の線引きを整理しておくこと => 対応範囲の明確化
- 4.信頼できるアフターサービスの外注先を選ぶための5つのチェックポイント
- 4.1.ポイント①アフターサービスの実績を確認できるか?
- 4.2.ポイント②アフターサービスの対応品質を確認できる資料があるか?
- 4.3.ポイント③担当者と直接話せる機会があるか?
- 4.4.ポイント④委託業務に関する報告の頻度や内容が契約前に明示されているか?
- 4.5.ポイント⑤外注会社内で過去の記録情報を蓄積している体制か?
- 5.アフターサービス外注化の第一歩目は「何をどこまで外注できるか?」から
住宅会社が抱えるアフターサービスの課題とは?

住宅業界において、アフターサービスは施主満足度を左右する重要な要素として認識されています。しかし多くの住宅会社では、その重要性を理解しつつも実務面で様々な課題に直面しているのが現状です。
ここでは以下3つの課題を取り上げ、それぞれ解説していきます。
- 担当者の人手が足りず、対応スピードや品質を維持できない
- 定期点検やトラブル対応などが属人化し、品質のバラつきが生じている
- 社内スタッフの負担が大きく、コア業務に集中できない
担当者の人手が足りず、対応スピードや品質を維持できない
まず一つ目の課題として、担当者の人手不足により、対応スピードや品質の維持が困難になっているケースが挙げられます。
例えば、繁忙期には複数の施主から同時に依頼が入るため、対応が1週間以上遅れるといった状況が発生し、「早く見に来てほしい」という施主の不満につながっています。また、人手不足により一人当たりの担当件数が増加することで、一件あたりの対応時間が短くなり、十分な説明や丁寧な作業ができないというケースも見られます。
結果として、「アフターフォローが行き届いていない」という施主からの評判を招き、新規顧客獲得にも悪影響を及ぼしかねません。人手不足は単なる業務の遅延だけでなく、企業の評判や信頼性にも関わる深刻な問題なのです。
定期点検やトラブル対応などが属人化し、品質のバラつきが生じている
二つ目の課題は、定期点検やトラブル対応などの業務が特定の社員に依存する「属人化」の進行です。
具体的には、「○○さんしか我が家の状況を知らない」と施主が特定の担当者を指名するケースや、マニュアル化されていない暗黙知に基づく対応が行われるため、担当者が休暇や退職した際に適切な対応ができなくなるといった事態が発生しています。
ある住宅会社では、ベテラン担当者の突然の退職により、その担当者が管理していた約100件の顧客情報と対応履歴が十分に引き継がれず、新任担当者が一から関係構築をやり直すという事態に陥りました。
属人化はサービス品質のバラつきを生むだけでなく、企業としての持続可能性を脅かす大きなリスク要因となっているのです。
社内スタッフの負担が大きく、コア業務に集中できない
三つ目の課題として、アフターサービス業務に社内スタッフが忙殺されることで、営業や設計といった本来のコア業務に集中できないという悩みがあります。
たとえば、新規の提案や打ち合わせの最中に、既存顧客からの緊急トラブル連絡が入り、その対応に追われるといったケースは日常的に発生しています。あるデザイナーズ住宅を手がける会社では、設計担当者がアフターメンテナンスの相談対応に1日の3分の1以上の時間を取られ、新規物件の設計スケジュールに遅れが生じるという問題が常態化していました。
本来、新たな付加価値を生み出すべき人材が、対応業務に時間を奪われることで、顧客獲得と企業の成長機会を逃しているというリスクがあるわけです。
このような状況を背景に、「すべてを社内で抱えきれない」と判断し、信頼できる外部パートナーとの連携を模索する企業が年々増加傾向にあります。アフターサービスの外注化は、単なるコスト削減策ではなく、業務効率化と顧客満足度向上の両立を図るための戦略的な選択肢として注目されているのです。
アフターサービスの外注に対してなぜ不安を感じてしまうのか?

では、アフターサービスの外注化を検討しようとしても、住宅会社の多くはその必要性を感じながらも不安を感じて一歩を踏み出せずにいるように感じます。なぜ住宅会社は、外注に対して不安を感じてしまうのでしょうか。その背景には、施主との信頼関係を損なうリスクへの懸念があると考えられます。
ここでは、外注に対する不安の本質と、それを乗り越えるための考え方について掘り下げていきます。
「外注=品質が落ちる」と思ってしまうから
住宅会社がアフターサービスの外注に躊躇する主な理由として、「品質低下への懸念」が挙げられます。この不安は大きく3つの要素に分類できるでしょう。
- 施主とのコミュニケーション:失礼な言葉遣いや対応をしないか?
- アフターサービスの品質:自社より低い品質を提供しないか?
- トラブル対応:責任の所在が分からないトラブルの対応が起こらないか?
まず、施主とのコミュニケーションにおいて、外注先が失礼な言葉遣いや対応をしないかという心配があります。住宅は高額な買い物であり、施主の期待値も高いため、一度でも不適切な対応があれば信頼関係が崩れかねません。
次に、アフターサービスの技術的な品質面で、自社より低いレベルの作業を提供されるのではないかという不安があります。住宅の不具合は専門知識を要するものも多く、適切な調査や修繕ができなければ、問題が拡大するリスクもあるためです。さらに、トラブル発生時の責任の所在が曖昧になり、適切な対応が遅れるのではないかという懸念も強いでしょう。
しかし実際には、アフターサービスを専門に担う外注先の多くは、住宅業界に特化したノウハウと豊富な現場経験を持っています。むしろ専門性に特化しているからこそ、会社の適切な選び方を理解すれば、外注でも高い対応品質を維持できることも十分可能です。
不安を感じるのは"施主への責任感"があるから
次に、外注に対する不安の根底に、「大切な施主との信頼関係を、自社の目が届かないところで壊してしまうのではないか」という強い責任感があるからでしょう。
施主との長期的な関係構築を重視する住宅会社だからこそ、この責任感は当然のことといえます。施主の満足度が企業の評判や将来の紹介受注につながる住宅業界において、アフターサービスの質は事業の根幹に関わる問題です。
しかし、だからといって「すべてを社内で抱える」という判断が最善とは限りません。人員や予算、技術といった社内リソースが限られる中で、すべての業務を完璧に遂行することは現実的ではないからです。むしろ、信頼できるパートナーに足りないリソースを補完してもらう体制を構築することで、自社の強みに集中し、結果として会社全体の品質をより安定して提供できるようになるケースも多く見られます。
住宅保証は従来、主に「何か問題が発生した時の補償」という側面が強調されてきました。しかし、住宅購入者の長期的な視点への意識変化に伴い、住宅保証の役割も大きく変わりつつあります。ここからは、保証サービスに対する認識がどのように変化しているのか、そして金銭補償以外にどのような価値が見出されるようになったのかについて詳しく見ていきます。
アフターサービスの外注検討の際に注意すべき点3選

アフターサービスに対する不安も、外注を「丸投げ」ではなく「パートナーシップ」と捉え、適切な連携体制を構築できれば、施主への責任を果たしながらも、自社の業務効率化と成長を両立させることが可能だと考えられそうです。
特に、住宅会社が感じやすい「施主対応がしっかりしているか」「技術レベルは問題ないか」「情報共有ができているか」といった不安を解消するためには、次の3つの点に注意することが重要です。
注意点①|施主との対応窓口を一元化しておくこと => 施主対応の標準化
アフターサービスを外注化する際の最大の課題は、情報の分断による対応の遅れやミスが発生するリスクです。外注先とのやりとりを複数の担当者がバラバラに行っていると、報告が抜けたり情報が重複したりして、結果的に施主の信頼を損なう原因となります。こうした事態を防ぐためには、社内に外注専任の窓口を設け、情報の出入口を一本化することが有効です。
具体的には、社内で「外注管理責任者」を任命し、すべての連絡や報告がこの担当者を通じて行われる体制を整えることで、情報の統一管理が可能になります。また、外注先に対しても、連絡窓口となる担当者を明確に指定してもらうことで、相互の連絡体制が整い、報告漏れや対応ミスを未然に防止できるでしょう。
窓口の一元化により、「誰に何を伝えればいいのか」という混乱がなくなり、施主から問い合わせがあった際にも迅速かつ正確に対応できる体制が整います。さらに、定期的な情報共有の場を設けることで、課題の早期発見や対応方針の統一化も図れるため、施主にとっても一貫性のあるサービスを提供することが可能になるのです。
注意点②|過去の対応内容を管理しておくこと => 対応品質の見える化
アフターサービスの品質を維持するためには、「どの施主に、いつ、どんな対応をしたのか」という履歴を社内でも確認できる仕組みを整えることが不可欠です。報告書、写真、点検記録などの情報を体系的に管理し、必要な時にすぐに参照できる状態にしておくことで、外注先の業務内容の可視化が実現します。
このような情報の可視化は、外注先への信頼を深めるだけでなく、施主に対しても安心感を提供することにつながります。たとえば、施主からの問い合わせに対して「先月の点検では〇〇という状況でした」と即座に回答できれば、外注であっても自社が状況を把握していることを示せるからです。
さらに効果的なのは、外注先にも顧客情報や過去のやり取りを適切に共有することです。「この施主は以前こんな相談をしていた」という背景情報を理解した上で対応できれば、より施主の状況に合わせたきめ細かなサービスが可能になります。クラウド型の顧客管理システムの活用や、定期的な情報共有ミーティングの実施などを通じて、社内と外注先の双方が同じ情報を基に対応できる環境を整えることが、外注の品質を高める重要なポイントとなるでしょう。
注意点③|内製と外注の線引きを整理しておくこと => 対応範囲の明確化
アフターサービスの外注を成功させるためには、「何を外注し、何を社内で行うか」という役割分担を明確にすることが重要です。すべての業務を丸投げするのではなく、それぞれの強みを活かした最適な分担を考えることが、効率的かつ高品質なサービス提供につながります。
例えば、緊急性の高い不具合対応は機動力のある外注先に任せる一方、定期的な面談や追加提案など施主との関係構築に直結する業務は社内スタッフが担当するといった分担が考えられます。また、軽微な修繕は外注、大規模な工事が必要なケースは社内の技術者が関与するなど、案件の規模や性質に応じた振り分けも効果的でしょう。
このような分担ルールをあらかじめ明文化し、社内外で共有しておくことで、業務の重複や抜け漏れを防止できます。さらに、定期的に役割分担を見直す機会を設けることで、運用の中で生じる課題にも柔軟に対応できる体制が整います。内製と外注の線引きを明確にすることは、外注先との健全なパートナーシップ構築の基盤となり、結果として施主に対する一貫性のあるサービス提供を可能にするのです。
信頼できるアフターサービスの外注先を選ぶための5つのチェックポイント

上記の注意点を踏まえアフターサービスの外注導入を検討する際は、「誰に任せるか」が成果を大きく左右します。住宅会社が感じる"品質への不安"を解消するためには、以下の5つの観点で外注先を見極めることが重要です。
ポイント①アフターサービスの実績を確認できるか?
外注先選定の第一歩は、その会社の実績を確認することです。単に「アフターサービスを行っています」というだけでなく、具体的な数字で実績が示されているかどうかが重要なポイントとなります。例えば、「年間500件の点検対応実績」や「住宅業界での10年の継続実績」など、具体的な数値が公表されていれば、それだけ豊富な経験があるという安心材料になるでしょう。
また、実績の量だけでなく質も重視すべきです。どのような住宅会社と取引しているか、どういった種類の案件を多く扱っているかなど、自社のニーズに合った経験を持っているかを確認することも大切です。例えば、木造住宅が主力の会社なら、木造住宅の点検や修繕に精通している外注先を選ぶことで、より専門性の高いサービスが期待できます。
実績確認の際には、可能であれば取引先の住宅会社からの評価や口コミも参考にすると良いでしょう。外注先から紹介してもらえる取引先があれば、直接話を聞くことで、数字だけでは見えてこない信頼性や対応力を把握することができます。長期的なパートナーシップを築くためには、安定した実績に裏付けられた信頼性が不可欠なのです。
ポイント②アフターサービスの対応品質を確認できる資料があるか?
外注先の品質を事前に評価するためには、具体的な業務成果物を確認することが効果的です。点検レポートや作業完了報告書のサンプルを見せてもらい、その内容の充実度や分かりやすさをチェックしましょう。写真付きで丁寧に記録されているか、専門的な内容をわかりやすく説明しているかなど、細部にわたって確認することで、実際の業務品質をイメージすることができます。
特に重視したいのは、施主向けの説明資料の質です。専門用語を多用せず、施主にもわかりやすい表現で説明できているか、不具合の原因や対処法が明確に記載されているかなどは、施主とのコミュニケーション能力を測る重要な指標となります。また、報告書のデザインや体裁が整っているかという点も、施主に与える印象に直結するため見逃せないポイントです。
さらに、作業手順書やマニュアル類も可能であれば確認したいところです。標準化された作業プロセスが確立されているかどうかは、安定したサービス品質を維持できるかの判断材料になります。外注先が独自に開発した点検チェックリストや品質管理基準があれば、それだけ業務への真摯な姿勢が伺えるでしょう。
対応品質を示す資料の充実度は、外注先の仕事に対する真剣さと専門性を反映するものなのです。
ポイント③担当者と直接話せる機会があるか?
外注先を選ぶ際には、契約内容や価格だけでなく、実際に現場で対応する担当者と直接コミュニケーションを取る機会を設けることが重要です。電話やWeb面談、可能であれば訪問など、何らかの形で担当者と事前に話すことで、コミュニケーション能力や対応の丁寧さ、専門知識の深さなどを直接確認することができます。
特に注目したいのは、質問に対する応答の正確さや迅速さです。こちらの疑問や懸念に対して、明確かつ具体的な回答が得られるかどうかは、実際の業務においても同様の対応が期待できるかどうかの指標となるでしょう。また、担当者の身だしなみや言葉遣いも、施主対応の質を左右する重要な要素です。
さらに、担当者との会話を通じて、その会社の企業文化や価値観も垣間見ることができます。「施主の立場に立った対応」や「丁寧なコミュニケーション」などの理念が、実際の担当者の言動に反映されているかどうかを見極めることで、表面的な営業トークではなく、真の企業姿勢を理解することが可能になります。
実際に対応する担当者との直接のやり取りは、数字や資料だけでは分からない「相性」を確認する貴重な機会なのです。
ポイント④委託業務に関する報告の頻度や内容が契約前に明示されているか?
アフターサービスの外注において、業務の透明性は信頼関係構築の基盤となります。そのため、どのタイミングで、どのような内容の報告を受けられるのかが、契約前に明確に示されているかどうかは重要なチェックポイントです。例えば、「対応後3営業日以内に報告書を提出」「月次で活動サマリーを共有」といった具体的な報告サイクルが明示されていれば、期待値と実際のサービスのズレが生じにくくなります。
報告内容についても、「写真3点以上と対応内容の詳細コメント」「施主の反応や追加要望の記録」など、具体的な項目が定められていると、必要な情報が漏れなく共有される仕組みが担保されます。また、緊急時や重大な不具合発見時の特別報告ルールが設定されているかどうかも確認しておくべきでしょう。
報告形式についても事前に確認しておくことが望ましいです。紙の報告書なのか、データでの共有なのか、専用システムへの入力なのかによって、社内での情報管理方法も変わってきます。自社の業務フローに合わせた報告形式が選べるか、あるいは柔軟に対応してもらえるかという点も、スムーズな連携のためのポイントとなるでしょう。
適切な報告体制が確立されていることで、「外注したら見えなくなる」という不安を解消し、常に状況を把握した上でのマネジメントが可能になるのです。
ポイント⑤外注会社内で過去の記録情報を蓄積している体制か?
長期的に安定したアフターサービスを提供するためには、外注先が過去の対応履歴を適切に管理・活用できる体制を整えているかどうかが重要です。「前回いつどんな対応をしたか」「以前どんな指摘やクレームがあったか」といった情報を、外注会社側でも確認できる仕組みがあるかを確認しましょう。
情報の蓄積体制が整っていることで得られるメリットは多岐にわたります。まず、対応ミスや重複対応を防止できるため、施主に無駄な負担をかけることがありません。また、担当者が変わっても一定の品質を維持できるため、人員変更による影響を最小限に抑えられます。さらに、蓄積されたデータを分析することで、季節ごとの不具合傾向や経年による劣化パターンなど、予防的な対応につながる知見も得られるでしょう。
具体的には、顧客管理システムの有無やデータベースの運用状況、情報セキュリティ対策などを確認すると良いでしょう。また、担当者間での情報共有方法や引継ぎプロセスについても質問してみることで、組織としての情報管理能力を判断する材料となります。
特に複数回にわたる定期点検や長期間のアフターサポートを委託する場合は、この体制の有無が安心感と継続的なサービス品質に直結するため、慎重に確認すべきポイントです。
アフターサービス外注化の第一歩目は「何をどこまで外注できるか?」から

今回ご紹介したアフターサービスの外注先選定における注意点や適切な選定基準が、住宅会社が抱える「アフターサービスの外注に対する不安」解消に少しでもお役に立てれば幸いです。特に、外注先の選定基準をしっかりと理解し、「何をどこまでを外注し、どこを自社で担うのか」を明確にしておけば、外注先との信頼関係も築きやすくなり、結果的にアフターサービスの品質を高く保つことができるでしょう。
アフターサービスの外注化は、すべてを一度に移行する必要はありません。例えば、まずは定期点検の一部だけを委託してみる、特定のエリアに限定して試験的に導入するなど、段階的に進めることで、リスクを抑えながら最適な運用方法を見つけることができるでしょう。また、内製・外注・併用のハイブリッド型を採用することで、それぞれの強みを活かしたバランスの良いサービス提供体制を構築することも可能です。
重要なのは、外注を「コスト削減のための手段」ではなく「施主との長期的な関係構築のための戦略的パートナーシップ」と捉える視点です。適切なパートナー選びと効果的な連携体制の構築により、外注を「不安」ではなく「武器」に変え、自社の競争力向上につなげることができるのです。まずはできるところから一つずつ外注化を実践し、自社にとって最適なアフターサービス体制を模索してみてはいかがでしょうか。
当社では、住宅会社様の多様なニーズに対応できるアフターサポートの幅広いサービスを各種ご用意しています。ご興味がありましたら、以下の詳細ページよりご覧下さい。



